 著者の英語には文法的間違い、また句読点の打ち間違いが多くあります。表現もぎこちなくイディオマティックではありません。全体的に洗練された滑らかさに欠けます。またこのホームページも同様です。これはなぜでしょうか。
著者の英語には文法的間違い、また句読点の打ち間違いが多くあります。表現もぎこちなくイディオマティックではありません。全体的に洗練された滑らかさに欠けます。またこのホームページも同様です。これはなぜでしょうか。

 よくある質問
よくある質問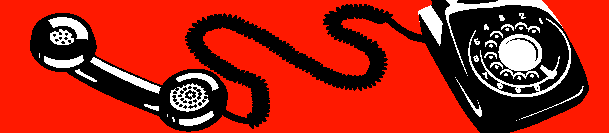
 著者の英語には文法的間違い、また句読点の打ち間違いが多くあります。表現もぎこちなくイディオマティックではありません。全体的に洗練された滑らかさに欠けます。またこのホームページも同様です。これはなぜでしょうか。
著者の英語には文法的間違い、また句読点の打ち間違いが多くあります。表現もぎこちなくイディオマティックではありません。全体的に洗練された滑らかさに欠けます。またこのホームページも同様です。これはなぜでしょうか。
 これは著者の英語力の限界を表わしています。著者はいわゆるネイティブ・スピーカーではなく、日本で生まれ育った生粋の日本人です。アメリカ、イギリスなどの英語圏に住んだことはおろか、旅行したことすらないのです。要するに英語が下手なのです。翻訳を頼むつてもなく、その金も、折衝にかける時間も惜しかったので、自分で書くのが一番と考えたのです。ただ出版に際してはアメリカのプロ編集者を雇って文章をチェックしてもらいました。
これは著者の英語力の限界を表わしています。著者はいわゆるネイティブ・スピーカーではなく、日本で生まれ育った生粋の日本人です。アメリカ、イギリスなどの英語圏に住んだことはおろか、旅行したことすらないのです。要するに英語が下手なのです。翻訳を頼むつてもなく、その金も、折衝にかける時間も惜しかったので、自分で書くのが一番と考えたのです。ただ出版に際してはアメリカのプロ編集者を雇って文章をチェックしてもらいました。
 では著者はどこで、またどのようにして英語を習ったのでしょうか。
では著者はどこで、またどのようにして英語を習ったのでしょうか。
 日本では中学までが義務教育です。そこで三年間習った後、さらに高校で三年間勉強を重ねました。著者は大学時代、英語の教科は選択しなかったので、学校での正式な英語教育を受けたのは以上の六年間だけです。そのほかは独学です。AFNラジオを聞いたり、コンピュータ・ソフトを使ったりしました。
日本では中学までが義務教育です。そこで三年間習った後、さらに高校で三年間勉強を重ねました。著者は大学時代、英語の教科は選択しなかったので、学校での正式な英語教育を受けたのは以上の六年間だけです。そのほかは独学です。AFNラジオを聞いたり、コンピュータ・ソフトを使ったりしました。
 この本に書かれている話は本当にあったことなのでしょうか。
この本に書かれている話は本当にあったことなのでしょうか。
 この話はフィクションです。しかしサブタイトルでうたっている通り、この小説は実際の出来事であるラムリー島攻防戦に材を取っています。英印軍のキャクピュ上陸作戦、オンドーの戦い、前田山の戦い、日本軍のミンガン・クリーク泳渡作戦などはすべて事実であり、できるだけ忠実に再現するよう心がけました。ただしこの作品のテーマであるワニ事件に関しては、一言述べなければなりません。
この話はフィクションです。しかしサブタイトルでうたっている通り、この小説は実際の出来事であるラムリー島攻防戦に材を取っています。英印軍のキャクピュ上陸作戦、オンドーの戦い、前田山の戦い、日本軍のミンガン・クリーク泳渡作戦などはすべて事実であり、できるだけ忠実に再現するよう心がけました。ただしこの作品のテーマであるワニ事件に関しては、一言述べなければなりません。
一般に事実として語られるのは「第二次世界大戦末期の1945年2月19日、ビルマ、ラムリー島で連合軍の包囲を突破し大陸へ脱出しようとした日本軍歩兵隊が、途中イリエワニに襲われ千名近くが命を落とした。生存者は約二十名に過ぎなかった」というもので、ワニによる世界最大の獣害としてギネスブックにも登録されています。
しかし旧軍の戦闘詳報を始めとする公式記録、また帰還兵士の戦記、覚え書きはこぞって、少なくとも四百五十名の兵が無事に島から脱出し大陸側にたどり着いたことを裏付けています。前述の数字と明らかに矛盾します。この話の信憑性には大いに疑問の余地があります。もし本当にワニによる襲撃があったとすれば、現実はこの本に書かれているようなことだったと推察しています。
 ラムリー・ワニ事件に関するギネスブックなどの記述では、「八百名から千名の日本兵が犠牲になった」とか「翌朝までの生存者は二十名に過ぎなかった」などと具体的な数字が挙げられています。信憑性はあるように思われますが、この点はどうでしょうか。
ラムリー・ワニ事件に関するギネスブックなどの記述では、「八百名から千名の日本兵が犠牲になった」とか「翌朝までの生存者は二十名に過ぎなかった」などと具体的な数字が挙げられています。信憑性はあるように思われますが、この点はどうでしょうか。
 当時はワニが世界各地で乱獲される前で、イリエワニの個体数も今よりはるかに多かったと思われます。群棲するその習性を考慮に入れたとしても、狭く浅い海峡で一晩で何百人もが一度にワニの餌食になるのは不自然です。八百から千名というのは当時の日本陸軍歩兵隊の一個大隊に相当します。英軍情報機関は、侵攻作戦に先立って歩兵第百二十一連隊が ラムリー島守備を担当していること、また上陸作戦時にはそれが一個大隊まで縮小されていたことまで正確に把握していました。結果的に一個大隊勢力の守備隊を掃討することに成功したため「八百名から千名」との数が英軍側の記録に残り、それが間違って伝えられていったのでしょう。
当時はワニが世界各地で乱獲される前で、イリエワニの個体数も今よりはるかに多かったと思われます。群棲するその習性を考慮に入れたとしても、狭く浅い海峡で一晩で何百人もが一度にワニの餌食になるのは不自然です。八百から千名というのは当時の日本陸軍歩兵隊の一個大隊に相当します。英軍情報機関は、侵攻作戦に先立って歩兵第百二十一連隊が ラムリー島守備を担当していること、また上陸作戦時にはそれが一個大隊まで縮小されていたことまで正確に把握していました。結果的に一個大隊勢力の守備隊を掃討することに成功したため「八百名から千名」との数が英軍側の記録に残り、それが間違って伝えられていったのでしょう。
またラムリー島攻防戦を通じて英印軍は日本軍から約二十名の捕虜を取り、チッタゴンの捕虜収容所に移送しました。日本軍の戦陣訓は「生きて俘囚の辱めを受くるなかれ」とうたい、兵士に対し捕虜になることを戒めていました。そのため孤立した日本軍守備隊は多くの場合玉砕戦法を取り入れ、多くの悲劇を生んでいたのですが、大戦も末期になると、さすがに心身ともに疲弊した兵隊には士気の低下が見られ、次第に捕虜になる者も現れていたのです。「二十名の生存者」というのはおそらくこの数から来たと考えられます。
 著者は前書きのなかで、一般に知られているラムリー島での大量殺戮の可能性を否定しながらも、日本軍占領地域ではワニによる人身事故がたくさんあったと述べています。具体的にはどのようなことですか。
著者は前書きのなかで、一般に知られているラムリー島での大量殺戮の可能性を否定しながらも、日本軍占領地域ではワニによる人身事故がたくさんあったと述べています。具体的にはどのようなことですか。
 概していえば、作品中に書かれているような事件が各地であったと考えています。そのほとんどは記録されることなく歴史の闇に消えていったのだと思いますが、それでも数多くの元兵士が戦記、回想録にワニによる人身事故を著しています。
概していえば、作品中に書かれているような事件が各地であったと考えています。そのほとんどは記録されることなく歴史の闇に消えていったのだと思いますが、それでも数多くの元兵士が戦記、回想録にワニによる人身事故を著しています。
ここにいくつか紹介します。著者の大学の先輩に水木しげるという人がいます。今では「ゲゲゲの鬼太郎」などの代表作により日本では知らない人がいないほど有名な漫画家なのですが、戦時中は徴兵され南方戦線の激戦区ニュー・ブリテン島へ送られていました。水木氏の「ラバウル戦記」によると、ある時現地で幅百メートルほどの濁った川を渡っている最中に、突然ワニが現れ一緒にいた初年兵をさらっていったそうです。恐ろしくなった水木氏は以後渡河の際は現地人のカヌーを使うようになったそうです。それでも再びワニに追いかけ回され、カヌーの操作を誤って水中に放り出されたことがあり死ぬほど怖い思いをしたと述懐されています。
また著者の故郷には歩兵百四十三連隊(宇野フォース)の一員として第一次アキャブ作戦(三十一号作戦)に参加した知り合いがいます。その人はマユ半島での作戦行動中、水路を連日足がふやけるまで歩かされ辛い思いを強いられた上、補給が劣悪で常に飢えに苦しんでいたといっていました。空腹に耐えられず何度か仲間とワニを狩ろうとしたことがあったそうです。ワニの肉は、現在でも東南アジアやオーストラリアで珍味として売られているように、なかなかの美味らしいと聞き及んでいたからだそうです。ワニはなかなか賢く、こちらが狩ろうとすると巧みに逃げ、兵隊たちが油断をしていると逆に襲ってくる恐ろしい動物で、文字通り食うか食われるかだったそうです。
 いつ、どのようなきっかけでこの作品を書こうと思ったのですか。
いつ、どのようなきっかけでこの作品を書こうと思ったのですか。
 最初にラムリー・ワニ事件を知ったのはやはりギネスブックです。正確には覚えていませんが1980年代だったと思います。非常に忌わしい事件だと思い、詳しく書かれた本を探したのですが一向に見つかりませんでした。それでこれはもう自分で書くしかないと考えたのです。
最初にラムリー・ワニ事件を知ったのはやはりギネスブックです。正確には覚えていませんが1980年代だったと思います。非常に忌わしい事件だと思い、詳しく書かれた本を探したのですが一向に見つかりませんでした。それでこれはもう自分で書くしかないと考えたのです。
 書き上げるまでどれぐらいの日数がかかりましたか。
書き上げるまでどれぐらいの日数がかかりましたか。
 概算で取材に三年、執筆に一年、英語に翻訳するのに一年、出版まで一年、全体では七年近くかかっています。
概算で取材に三年、執筆に一年、英語に翻訳するのに一年、出版まで一年、全体では七年近くかかっています。
 次回作の予定がありますか。またあるのであればどのような作品ですか。
次回作の予定がありますか。またあるのであればどのような作品ですか。
 第二次世界大戦中の日本軍にまつわるものをもう一本準備中です。今度は対ソ連の北方戦線に材を取ったものになりそうです。ただ著者は日本語で執筆するため、英語版をいつ発表できるかについてはあまりに先の話過ぎて、現時点では見込みはまったく立っていません。
第二次世界大戦中の日本軍にまつわるものをもう一本準備中です。今度は対ソ連の北方戦線に材を取ったものになりそうです。ただ著者は日本語で執筆するため、英語版をいつ発表できるかについてはあまりに先の話過ぎて、現時点では見込みはまったく立っていません。