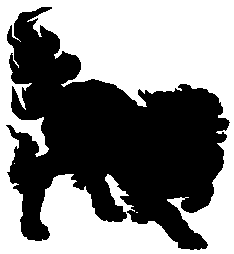
「唐獅子」と呼ばれる。ライオンのイメージが中国大陸経由で伝わったためこのように呼ばれる。日本にも中国にもライオンは生息していないので、架空の動物といった方が正確。伝統美術のテーマとして好まれた。よく牡丹の花と組み合わせてデザインされる。


 日本文化
日本文化淡路島
瀬戸内海(the Inland Sea of Japan)に浮かぶ同海最大の島。ラムリー島と同じくらいの大きさ。形状も似ている。
唐獅子
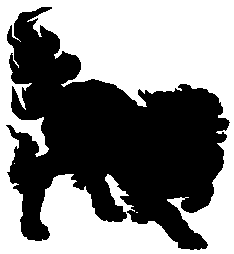
「唐獅子」と呼ばれる。ライオンのイメージが中国大陸経由で伝わったためこのように呼ばれる。日本にも中国にもライオンは生息していないので、架空の動物といった方が正確。伝統美術のテーマとして好まれた。よく牡丹の花と組み合わせてデザインされる。
米つき
米は脱穀し精米しないと炊くことができず、食べられない。戦地の兵は鉄帽や一升瓶にもみを入れて米をつくことが一般的だった。
サイダー
文中のサイダーとはラムネのこと。なぜか当初「レモネード」といわれて西洋から渡来した炭酸飲料。その後、なまって「ラムネ」と呼ばれる。飲み口の栓としてビー玉が使われる独特の形状のビンに入っている。最近はあまり見かけなくなった。
戦国時代

1467年の応仁の乱以降、室町幕府の権威は地に落ち、その権力を背景にした守護大名は各地に興った戦国大名に次々に倒され、日本は群雄が覇を競う動乱、内戦の時代に突入した。1568年、織田信長入京に至るまで続き、以後は統一の時代に向かう。
足袋
伝統的な袋状の履物。親指と他の指が分かれる形態のもの全般をさす。絹製の瀟洒なものから、作品中に書かれているワーク・ブーツ型まで、靴下、靴の区別を問わない。韓国人、朝鮮人が日本人の蔑称として用いる「豚足」とは、これを履くとそう見えることから来ている。
徳川時代
1600年関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康が戦乱の世に終止符を打ち、1603年将軍として江戸に幕府を開いた。武家政治が続いた中で比較的平和な時代。1867年の大政奉還まで続いた。
握り飯
代表的なファースト・フード。古い歴史を持つ一方、現代ではコンビニエンス・ストアで売られているほど人気がある。塩をまぶした米を固めて作る。梅干し、鮭などの具を入れたり、海苔で巻いたりとバリエーションが豊富。戦地では多くの場合、ただの米だけで作られることが多い。
能
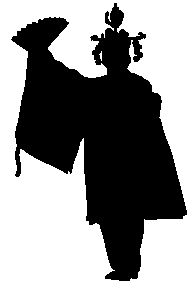
伝統演劇のひとつ。伴奏に合わせ謡い舞う一種の歌舞劇。舞台装置はほとんど用いず、面をかぶり豪華な装束をまとった演者の内面的、静的な表現が特徴。
腹切り
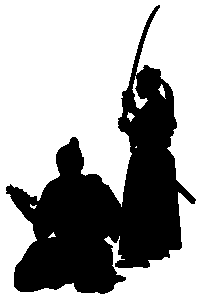
武士だけに許される最上位の謝罪方法。徳川時代には武士に対する刑罰のひとつになった。切腹するところを介錯人が首を打つ。これにより多少の名誉が死者に与えられ、面目を保つことができた。罪人の首を完全にはねてしまう打ち首とはこの点で異なる。戦時中は乱用され、多くの悲劇を生んだ。
ふんどし
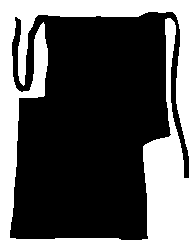
日本では「ふんどし」と呼ばれる。古来からの男性専用の下着。越中(現富山)型のものが一般的。戦後はほとんど廃れたが、現在でもデパートに行けば買える。
鳳凰
中国で神聖視された想像上の鳥。麒麟の前半身、鹿の後半身、蛇の首、魚の尾、つばめの顎、鶏のくちばし、亀の背中、五色の羽を持つといわれている。支離滅裂なほどに複雑なので、実際は西洋のものと近いイメージで描かれることがほとんど。
麺類
「うどん」と「そば」が代表的。「うどん」は小麦粉を塩水でこねて薄くのばし、細く切ったものをゆでて食べる。そば粉、卵白、山芋を加えたものが「そば」。どちらも日本の食文化にとってなくてはならない存在。