
ピラミッド内部でもセベックに関する記述が発見されている。おそらく渡河の際の鰐の恐怖がこの神を生んだのだろう。セベックについては、有名な「死者の書」に詳細が書かれている。


 宗教
宗教古代エジプト
コム・オンボ神殿
ここは鰐の聖域で、セベック信仰の中心だったと思われる。現在でも一室が観光客に開放され、発掘された鰐の棺を見ることができる。セベックにまつわる遺跡には、ほかにメディネット・マディ神殿がある。
セベック

ピラミッド内部でもセベックに関する記述が発見されている。おそらく渡河の際の鰐の恐怖がこの神を生んだのだろう。セベックについては、有名な「死者の書」に詳細が書かれている。
神社
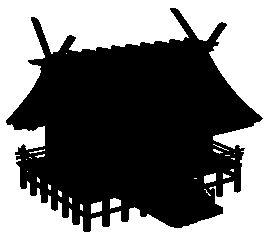
神道は日本で発生、発展した民族宗教。自然、祖先の崇拝を中心とする。明治以降の近代には国家の管理下に入り、政治的に利用された。戦後は国家の保護を離れ民俗的信仰としての本来の姿に戻った。神殿は「神社」と呼ばれる。神霊を奉安する「本殿」、礼拝を行う「拝殿」、神域を示す門「鳥居」などから構成される。八幡造りを始め、さまざまの建築様式がある。
八幡
応神天皇を主座とするらしい。古代より広く信仰された弓矢、武道の神。守護神としてとくに武士に人気があった。
御輿
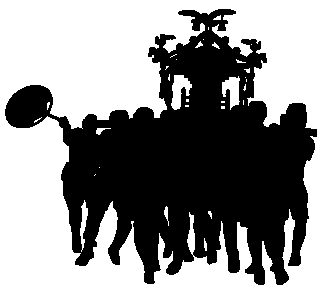
神霊が乗るとされる輿。屋上に鳳凰などのモチーフが絢爛豪華にかざられたものが、日本各地の祭りで使われる。多くの担ぎ手がねり歩くさまは勇壮で、観光風物になっている。
鳥葬
紀元前六世紀ペルシャの預言者ゾロアスターによって創始されたこの宗教は、イスラム教の興隆とともにすたれた。しかし21世紀の現在でも鳥葬はなおも隆盛で、チベットでは、聖なる禿鷲の生息域を保護するため鉄道会社が路線計画を変更するほどだ。
釈迦涅槃像
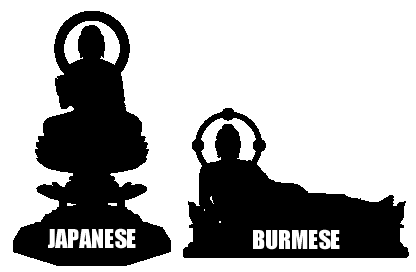
クシナガラ(Kusinagara)で釈迦が沙羅双樹の下で入滅する姿をモチーフとする仏像。釈迦如来の仏像としては、座像が中心の日本に対し、ビルマではこちらの方が一般的。
パゴダ
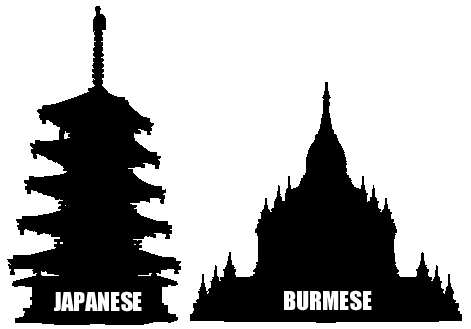
東南アジアの卒塔婆(stupa)。本来は釈迦の遺骨、遺髪、遺品などを埋めた盛り土の上に建てられた仏塔。日本の物とは大きく形が異なる。
龍

古代インドで蛇を神格化した架空の動物。中国では雲を起こし雨を呼ぶといわれた。仏教では仏法を守護する天龍八部衆のひとつ。西洋のものとはイメージが違う。著者は鰐がモデルと考えている。