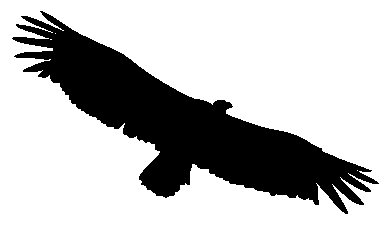
アフリカ、アジア、南欧に広く分布。南北アメリカ大陸に生息するコンドルとは別種。主食は死肉。多くは頭に羽毛がほとんどなく、この名がある。日本にも迷鳥として飛来した記録がある。


 動植物
動植物
ハゲワシ
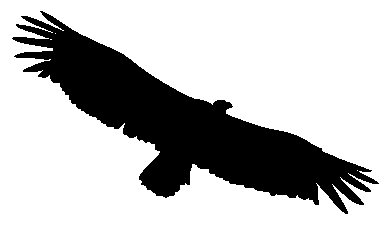
アフリカ、アジア、南欧に広く分布。南北アメリカ大陸に生息するコンドルとは別種。主食は死肉。多くは頭に羽毛がほとんどなく、この名がある。日本にも迷鳥として飛来した記録がある。
イリエワニ
インド東部、フィリピン、ニューギニア、オーストラリア北部に分布。塩水ワニ、インド太平洋ワニともいう。性質は荒く人畜を襲うこともあるが、 通常は魚類などを補食している。40から80個程度産卵し、孵化まで雌が保護する。
スイギュウ
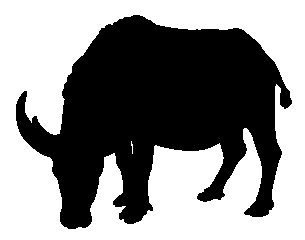
水辺に生息する牛の総称。タマラオ、アジアスイギュウなどがある。アジアスイギュウはインドスイギュウともいい、黒灰色。気性は荒いが家畜として東南アジア、南欧などで広く飼われている。熱帯性風土病に対して抵抗力が強い。アフリカ種は褐色が強く、サハラ以南に生息し、大群を作ることがある。
トビハゼ

全長約10センチ。目は頭頂部に突き出し、広い視野を持つ。主に干潟に生息し、小動物を補食する。胸びれを使い泥の上をはうことができる。
カニクイザル
オナガザル科に属し、東南アジアに広く分布。黄褐色で全長約1メートル。雑食性で特別カニを好むというわけではない。
マンゴー
南インド、タミール語の mankay に由来。man は樹名、kay は果実の意味。ウルシ科の常緑高木。東南アジア原産。黄色い花を付ける。古くから果樹として栽培されてきた。果肉は多汁で美味。
竹
東南アジアを中心に約40属 600種あるイネ科の植物。建築材、細工物、竿などに重用し、たけのこは食用。花は時には数十年といった長い周期で咲く。そのため各地で吉凶の前触れと信じられている。
ニッパヤシ
熱帯アジア、南太平洋諸島、オーストラリア北部のマングローブ地帯の湿地に生える。地上茎はなく、泥中の根茎から直接扇状の葉を付ける。葉は屋根葺きに用い、樹液からは砂糖がとれる。
ヒルギ
オヒルギ、メヒルギ、オオバヒルギなどヒルギ科の総称。マングローブを形成する。呼吸根を持ち特異な形態的特徴がある。