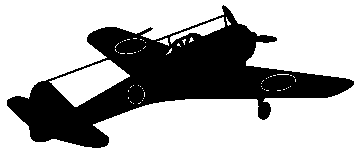
連合軍からは「オスカー」、日本では「隼」と呼ばれた。陸軍の戦闘機の大半がこれ。武装は12・7ミリ機銃二門。何度も改良が加えられ、多くの型式がある。


 日本軍武器
日本軍武器
一式戦闘機
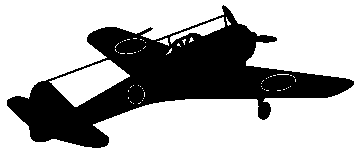
連合軍からは「オスカー」、日本では「隼」と呼ばれた。陸軍の戦闘機の大半がこれ。武装は12・7ミリ機銃二門。何度も改良が加えられ、多くの型式がある。
百式司偵

三菱製。最高速度時速343マイル。7・7ミリ機銃一門搭載。米軍は「ディナ」、もしくは「ダイナ」と呼んでいた。
九七式軽装甲車
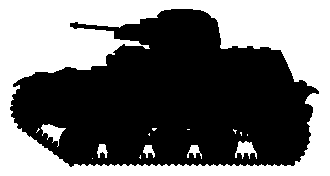
4・75トン。空冷直4ディーゼルエンジン搭載。武装は九四式37ミリ砲、または7.7ミリ車載重機関銃。二人乗り。もともとは弾薬運搬車として作られた。戦車の格好をしているが、装甲板の厚さは最大でも16ミリしかない。
37ミリ対戦車砲
日本最初の対戦車砲の口径は37ミリと決定された時点で、この基準はすでに時代遅れとなっていた。九四式、またドイツから輸入したラインメタル(Rheinmetall)式などがある。日本では速射砲(Infantry Rapid Fire Gun)と呼ばれていた。
大隊砲
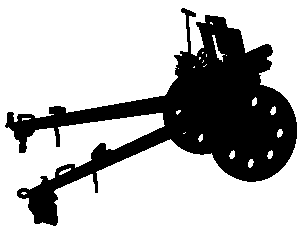
九二式歩兵砲が有名。口径70ミリ。命中精度が低く、振動も大きい。性能は決して高くないが、独特の設計の生んだ軽便さは、機動力の劣る日本軍にとっては重宝だった。さまざまな戦線で歩兵支援の役を果たし活躍した。
火炎放射器
九三式、百式が代表的だが、放射性能が低い割にバルキーで、兵の間では人気がなかった。生産代数も少なく一般的な武器とはいい難い。
九二式重機関銃

有効射程1400メートル。発射速度毎分450発。バランスがよく、射撃の振動が少ないので、命中精度に優れていた。信頼性も高く、歩兵戦闘の援護射撃のかなめとして用いられた。通常銃手四名、弾薬手四名で一銃を担当する。
擲弾筒
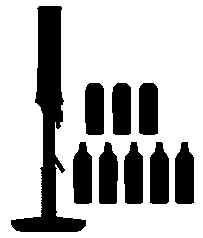
手榴弾をより遠くに放り投げようとの発想に基づく。八九式重擲弾筒が代表的。有効射程700メートル。安価で大量に生産された。ポータブルでフレキシブル。これによる奇襲は連合軍兵士を度々恐れさせた。
九六式軽機関銃

口径6・5ミリ。重量8・7キロ。発射速度毎分550発。広く使われたが、故障も多かった。日本で初めてバナナ型の弾倉を装着するなど近代的な設計。しかし突撃用に銃剣が付けられるようになっているなど前近代的な部分もある。採用前後に歩兵操典が改正され、時代に逆行する突撃重視の方針となったためだ。
破甲爆雷
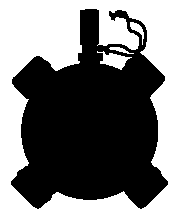
直径約12センチ。「アンパン」とか「亀」などと呼ばれた。本来の使用法のほか、手榴弾の代わりに直接敵に投げつけることもあった。
九三式地雷
円盤型のごく一般的なもの。対戦車、対人両方に用いられた。円周部分に環が付けられており、ここにひもを通して携帯する。
手榴弾
九一式、九七式などがある。日本の手榴弾はおおむね安全ピンを抜くことによってキャップをはずし、フューズを固いものに打ちつけることによって発火させる。ほかにドイツ式のスティック・タイプ型や、モロトフ・カクテル型火炎ビンなどもあった。
三八式歩兵銃

明治三十八年に完成し、翌年正式採用されたモーゼル型ボルト・アクション・ライフル。クリップ式5連発。当時の水準では優れていた。発射火が小さい上、反動が少なくよく当たった。しかし台頭する自動小銃の前に次第に苦戦を強いられる。また全長127センチと大きく、小柄な日本兵には扱いがやっかいだった。天皇から貸与されたものであることを示す菊の紋章が銃身後部に刻まれている。
三八式騎兵銃
単に馬に乗るのに便利なようにと上記の歩兵銃を約30センチほど短くしたもの。約600グラム軽い。「カービン」といっても自動式ではない。騎兵のほか、小柄な兵全般に支給された。
南部十四年式
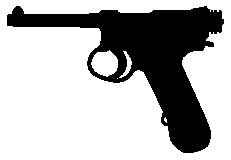
南部麒次郎中将設計の半自動拳銃。口径8ミリ。8連発。命中精度が高い。トリガー・ガードが異様に大きいのは、手袋をしたままでも撃てるように改良された結果。南部式は、ライフル型の銃床を装備したものや、サーベルの刃を取り付けた珍妙なものまであり、バリエーションが豊か。
軍刀
西洋型のサーベルと古来の日本刀が混在する。また反りの少ない「昭和新刀」と呼ばれるものが急造された。