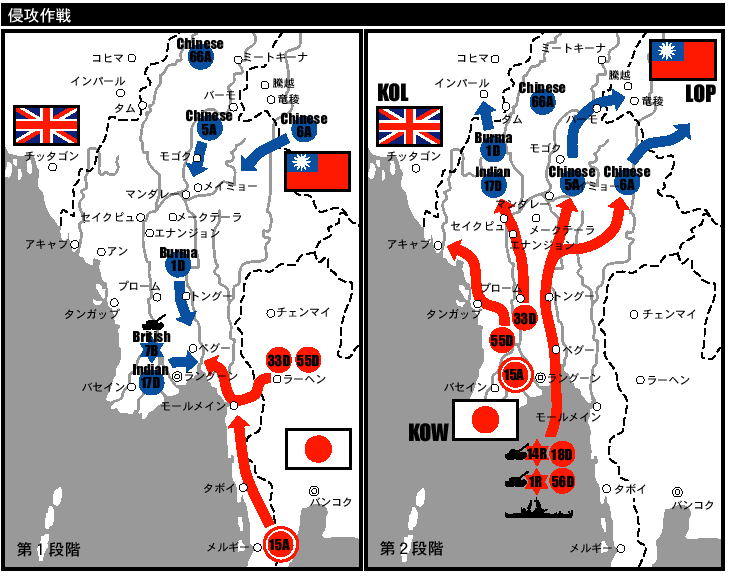
赤:日本軍 青:連合軍 二重丸:軍団以上の部隊 丸印:師団相当の部隊 星印:旅団以下の部隊 A:軍 D:師団 B:旅団 R:連隊
KOW:ノックアウト勝ち KOL:ノックアウト負け WOP:判定勝ち LOP:判定負け


 ビルマ戦線
ビルマ戦線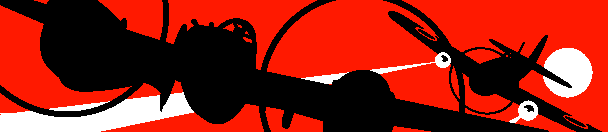
第二次世界大戦中連合国は、インド、東南アジア経由で蒋介石の中華民国国民政府に対し、さまざまの支援を行っていた。援蒋ルートと呼ばれるこれら補給路の内、ラングーンから雲南省への陸路はビルマ・ロードと呼ばれていた。この遮断を目的に大日本帝国は、イギリス連邦、中華民国、アメリカ合衆国、そして最後にはビルマとも戦火を交えた。
東南アジアの日本陸軍最高指揮官は南方総軍寺内寿一元帥。南方総軍はビルマからニューギニア、フィリピンに至る広範囲の南方戦線を管轄していた。
侵攻作戦
日本軍のビルマ侵攻作戦は、飯田祥二郎中将旗下第十五軍によって遂行された。 太平洋戦争が始まるやビルマ南部テナセリウム地方に進出した第十五軍は、メルギー、タボイの飛行場を奪取。1942年1月には竹内寛中将率いる第五十五師団基幹の主力部隊が、タイのラーヘンからコーカレーク峠を越えビルマに侵入。直ちに西進を開始した。迎え撃つ英印軍はインド第17師団基幹。しかしこの部隊は急造編成で、装備、訓練共に十分ではなく、サルウィン川河口、モールメインまで一気に押し込まれた。17師団はここで数日持ちこたえたが、川に阻害され補給を受けられず、ついに1月31日モールメインを放棄。更に西のシッタン川に向け後退を始めるが、日本軍の空襲に退却行動は滞った。シッタンに先着したのは、ジャングルを突破してきた桜井省三中将旗下第三十三師団だった。三十三師団は直ちにシッタン鉄道橋の確保に乗り出した。この脅威に17師団は2月22日、集結に遅れた味方を対岸に置き去りにしたまま橋梁を爆破してペグー方面に退却した。
その後イギリス第7機甲旅団などの増援を得た英印軍は反撃を試みるが、進撃する第十五軍の勢いを止めるには至らず、次々に拠点を落とした。首都ラングーンでは、英空軍と、アメリカ合衆国義勇軍「フライング・タイガース」が日本軍の空襲を何とか防いでいた。しかしテナセリウムの飛行場を得た日本軍航空隊の攻撃が、首都近郊の連合軍飛行場に及び始めると、その防空能力も低下した。英印軍は3月7日ついに港湾設備を破壊してラングーンを脱出。日本軍はシンガポール飛行場奪取以降、航空輸送力を既に増加させており、首都の海運、鉄道拠点を手に入れたことでその補給線は更に強固になった。一方、ラングーン喪失により陸、海、空すべての補給路を寸断されたイギリスに広域戦線を維持する力はもはやなく、ビルマ全面放棄は避けられなくなった。こうして始まった連合軍の撤退は、多数の民間人避難民を伴ったため、各地で大混乱になった。
北ビルマには蒋介石主席旗下中国国民政府軍が援軍として進出していた。しかし中国軍は日本軍を食い止めるどころか、その進撃を遅らせることすらできずに潰走した。中国軍のほとんどはサルウィン川を越えて雲南省に撤退したが、退路を断たれた一部は、米軍ジョゼフ・スティルウェル将軍と共にインドへの撤退を余儀なくされた。ビルマ戦線の中国軍は、その後兵力の回復に努め、米軍により再装備、再訓練された。
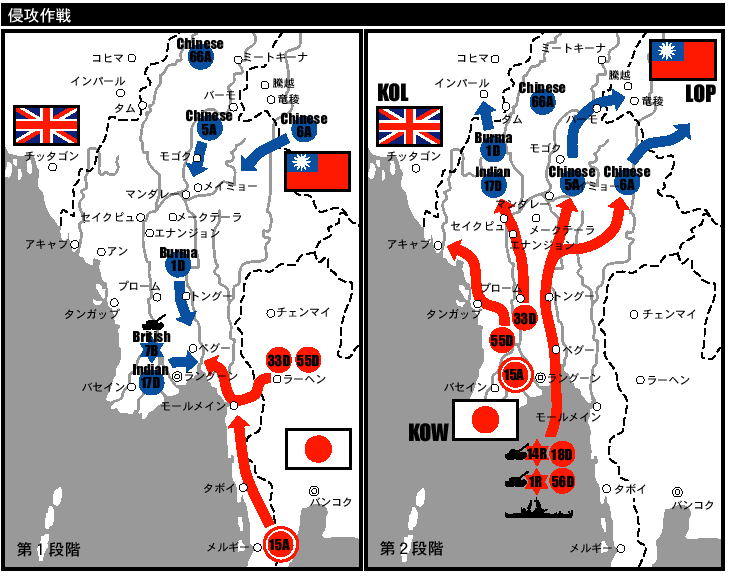
赤:日本軍 青:連合軍 二重丸:軍団以上の部隊 丸印:師団相当の部隊 星印:旅団以下の部隊 A:軍 D:師団 B:旅団 R:連隊
KOW:ノックアウト勝ち KOL:ノックアウト負け WOP:判定勝ち LOP:判定負け
第一次アラカン作戦
1942年から43年までビルマ戦線の連合軍は、中途半端な作戦しか展開できなかった。中東や北アフリカではドイツ軍が暴れていた。イギリスは既に多方面に戦線を抱えており、ビルマで即時反攻する余裕はなかった。従って当面のところ本国に近い戦線に集中せざるを得なかった。ロンドン、ワシントン両政府で取りかわした「ドイツ優先」政策も影響した。
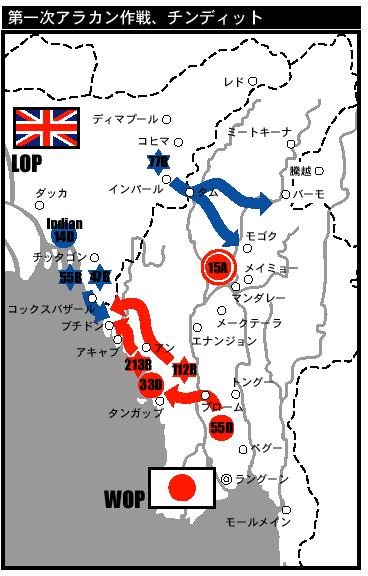 それでも42年から43年の乾期、イギリスはふたつの作戦を実行に移した。最初は後に「第一次アラカン作戦」と呼ばれる小規模な反攻だった。アラカンはベンガル湾に面した地方で、無数の河川が縦横に走る。代表都市アキャブには重要拠点の飛行場があった。マユ半島及びアキャブ島奪還を目的にこの地に攻め込んだイギリスは、最初から指揮系統に問題を抱えていた。ウィリアム・スリム中将の第15軍団は、東部軍のノエル・アーウィン中将によって、戦闘序列から外された。その一方で、単なる前線師団指令部に手にあまるほどの用兵が委ねられるといういびつなものになっていた。
それでも42年から43年の乾期、イギリスはふたつの作戦を実行に移した。最初は後に「第一次アラカン作戦」と呼ばれる小規模な反攻だった。アラカンはベンガル湾に面した地方で、無数の河川が縦横に走る。代表都市アキャブには重要拠点の飛行場があった。マユ半島及びアキャブ島奪還を目的にこの地に攻め込んだイギリスは、最初から指揮系統に問題を抱えていた。ウィリアム・スリム中将の第15軍団は、東部軍のノエル・アーウィン中将によって、戦闘序列から外された。その一方で、単なる前線師団指令部に手にあまるほどの用兵が委ねられるといういびつなものになっていた。
1942年12月、マユ半島を南下したインド第14歩兵師団は、先端までわずか数マイルに迫りながら、ドンベイクで日本軍小部隊に止められる。第三十三師団が前もってここに掩蓋陣地を張り巡らせていたのだ。英印軍は戦車支援もないまま強固な陣地に正面攻撃を繰り返し、その都度多数の死傷者を出して押し返された。その間、日本軍には中央ビルマから第五十五師団の援軍が到着。4月3日、棚橋真作大佐率いる歩兵第百十二連隊が、連合軍が踏破不能と判断した湿地、山岳地を突き抜けてインド第14師団の側面を急襲。指令部までも蹂躙され甚大な被害を受けた英印軍は、遅ればせながらスリム中将を指揮系統に投入し、戦線の立て直しを図った。押っ取り刀のスリムは、ブチドンの南に防衛線を張り直して持ちこたえようとした。しかしスリムもまた第三十三師団の攻撃を防ぎきれず、英印軍は結局インド国境まであえなく押し戻された。この一連の戦闘は日本側では公式には「三十一号作戦」と名付けられ、一般的には「第一次アキャブ作戦」と呼ばれている。
第一次チンディット
二番目の反攻作戦はインド第77歩兵旅団によるものだった。「チンディット」と呼ばれるこの部隊は、オード・ウィンゲート少将に率いられ諜報活動、後方撹乱を目的に日本軍占領地奥深くまで潜入した。この作戦は当初、大規模反攻の一環として計画された。しかし肝心の反攻作戦が輸送力不足で頓挫してしまい、チンディット単独の作戦に戦略的意味はなかった。それでもとにかく実行された。約三千の兵が小部隊に分かれてビルマに潜入し、第三十三師団の後方連絡線に被害を与え、軍事情報を収集した。チンディットは、各地で日本軍に掃討され多くの犠牲者を出し、作戦は勝利とはいい難い結果となった。しかし、ジャングルでも航空機による補給が可能なこと、またそれがあればイギリス兵、インド兵も日本兵同様ジャングルで十分生存、移動、戦闘できることを証明した。
転換点
1943年8月、連合軍は全東南アジア戦線の統合指揮を担当する「東南アジア戦域軍」を新設し、全ビルマ戦線の管轄を引き継がせた。イギリス第14軍は既に兵力を回復していた。攻勢はいつでも可能だった。連合軍補給線も強化されていた。戦争開始時一日600トンに過ぎなかった北東インド鉄道の輸送力は、1944年10月には一日4,400トンにまで引き上げられていた。英空軍は既に日本軍航空隊に対する数的優位を確立しており、連合軍の戦略の幅は広がっていた。
1943年後半、東南アジア戦域軍設立と同じころ、日本軍も陣容を整えていた。最高指揮官河辺正三大将の下「ビルマ方面軍」指令部が新設された。ビルマ方面軍は、南部戦線統括のため桜井省三中将を長に第二十八軍を編成し、中央ビルマ戦線担当の第十五軍と共に、その傘下に収めた。十五軍の司令官には牟田口廉也中将が着任した。牟田口は、長きに渡る日中戦争の発端となった盧溝橋事件の中心人物だった。太平洋戦争開戦以降はシンガポール陥落などの華々しい勝利に貢献しており、更なるインド侵攻作戦を熱望し、実際に計画していた。ビルマ方面軍は当初この作戦を無謀と判断し却下した。しかしシンガポールの南方総軍、東京の大本営は共に牟田口支持に回った。日本軍がインドに侵攻すればイギリスの支配体制崩壊は必定、とインド国民軍最高指揮官チャンドラ・ボースが東条英機首相を説得していたことが背後にあったといわれている。こうしてインド、インパールへの侵攻計画、「ウ号作戦」は認可され、直接攻撃を担当する前線師団指令部がこぞって作戦に不信を抱いているにも関わらず、実行に移された。
第二次チンディット
蒋介石中国軍支援のため、インド、レドから雲南に至る陸路、いわゆる「レド公路」を開通しようと、ジョゼフ・スティルウェル将軍は北ビルマへの反攻を計画していた。チンディットは旅団から師団へ強化され、新たにインド第3歩兵師団と改名されていた。スティルウェル旗下米中連合軍の作戦支援のため、チンディットはインドウ地方で日本軍補給路を撹乱、破壊することになった。これが「オペレーション・サーズデイ」である。1944年2月5日レドを発った傘下の第16旅団が後方地帯潜入に成功すると、チンディットは3月初旬アメリカ合衆国空軍第1航空総軍の協力で空挺作戦を行い、三個旅団を日本軍背後にグライダーで降下させた。
北ビルマ1943〜44年
ミートキーナ、モガウン付近に攻勢をかけるため、スティルウェル指揮下の中国軍第38師団は1943年10月、レドからシンビヤンに向け進撃を開始した。フーコン谷地進出後、日本軍第十八師団の防衛拠点に遭遇すると、フランク・メリル准将の「マローダーズ」部隊がジャングルを抜けて日本軍陣地の側面を突いた。これは開戦当初日本軍が用い成果を収めていた奇襲戦法だった。
雲南前線の中国軍も攻勢に転じていた。1944年4月、四万に迫る兵がサルウィン川を渡ると、数日の内に十二個師団七万二千の中国軍が第五十六師団に襲いかかった。北西に米中連合軍、北東に国民政府雲南遠征軍を迎え、北部戦線日本軍は二方面同時の戦いを強いられた。この統括のため、44年4月、本多政材中将を長に第三十三軍が設けられ、十八、五十六の二師団が傘下に入った。
スティルウェルの中国軍が戦果を重ねている内に、マローダーズは44年5月17日、ヒマラヤ山脈を越える空路の中継地として重要なミートキーナ飛行場を奪還した。こうしてスティルウェルは長期戦略の序盤を成功裏に終えた。
第二次アラカン作戦
アラカン戦線では、フィリップ・クリスティソン中将率いるインド第15軍団がマユ半島に進出。1944年1月9日インド第5師団にモウガンを占領させると、15軍団はモンドウとカラパンジン谷地をつなぐ鉄道トンネル確保に乗り出した。しかしこの前線で先制攻撃したのは、今回も日本軍だった。ビルマ方面軍はインパール侵攻に先立って、アラカンの第二十八軍に「ハ号」と命名された陽動作戦を準備させていた。英印軍の後方に潜入した第五十五師団の精鋭部隊は、インド第7師団を背後から急襲し、シンゼイワ盆地の指令部に迫った。しかし戦局は前回のアラカン戦と全く違ったものになった。英印軍は「アドミン・ボックス」と呼ばれる方法で陣地を円形に張り巡らせ、航空機による補給を受けながら前線を堅持した。2月5日から23日まで続いたこのアドミン・ボックスの戦いで、桜井徳太郎少将率いる第五十五歩兵団は、第7師団の指令部を集中攻撃した。指令部は後方勤務の兵が守っているだけだったが、戦車の支援を受けた守りは固く、結局崩すことはできなかった。英印軍兵士は訓練されていた。日本軍得意の潜入、包囲戦法に際して以前のように恐慌に陥り潰走することはなかった。敵物資収奪を前提にした日本軍の補給計画はたちまち破綻し、兵は飢餓にも苦しめられた。やがて、インド第5師団の援軍がアドミン・ボックス守備兵救出のためナケドウク峠を越えシンゼイワに到着すると、日本軍は封鎖を解いて後退せざるを得なくなった。この一連の戦闘は日本では「第二次アキャブ作戦」と呼ばれることが多い。両軍の死傷者数は大体同じだが、大局的には日本軍にとって手痛い敗北となった。
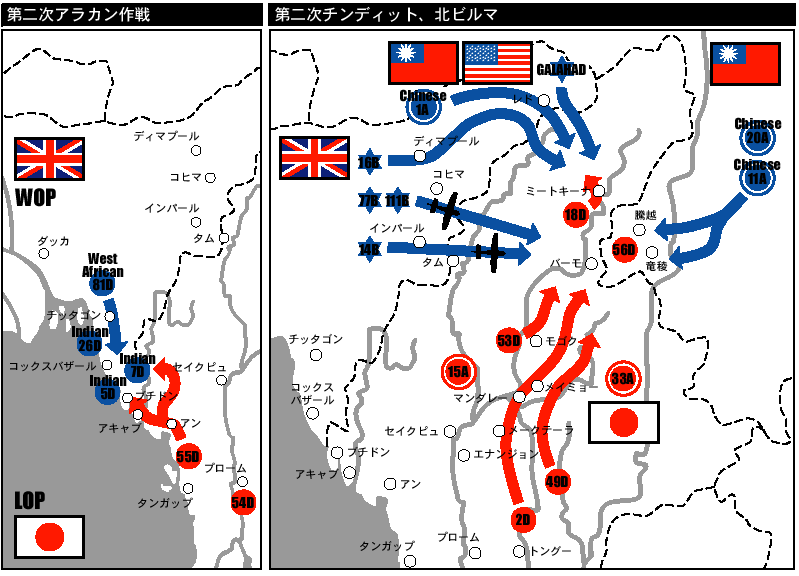
赤:日本軍 青:連合軍 二重丸:軍団以上の部隊 丸印:師団相当の部隊 星印:旅団以下の部隊
A:軍 D:師団 B:旅団 GALAHAD:米軍5307混成部隊 WOP:判定勝ち LOP:判定負け
インパール作戦
牟田口廉也中将旗下第十五軍(十五師団、三十一師団、三十三師団)指令部は、インパール攻略にはレジナルド・スクーンズ准将旗下第4軍団前衛師団の孤立化、粉砕が必要と考えていた。またディマプールからインパールへの敵の補給路を断つため、佐藤幸徳中将の第三十一師団に中継地コヒマを占領させる手はずを整えていた。野心家の牟田口はさらに三十一師団にディマプールを攻略させようとまで考えていた。ディマプールを制圧すれば、日本軍は山岳国境地帯を抜けて、北東インドのほとんど全域に攻勢をかけられる。インド国民軍部隊を攻撃に投入し、国内で反乱を惹起させることも可能になる。鉄道拠点を押さえれば、連合軍の対中支援ヒマラヤ越え空路を支える飛行場への陸上連絡路を断ち、同時にスティルウェル将軍配下北部戦線米中連合軍の補給線を断つこともできるのだった。
作戦発令と共に、日本軍は3月8日チンドウィン川を越え進撃を開始。新たに第14軍司令官に着任したスリム中将の指示により、第4軍団前衛は予定の退却に移った。インド第20師団はインパールまで遺漏なく下がったが、インド第17師団は急進してきた柳田元三中将の第三十三師団に退路をふさがれた。それでも17師団は、C−47ダコタ輸送機を駆る英米両空軍の空中補給部隊やインド第23師団の支援を受け、日本軍の封鎖を次々に突破しながらインパールを目指した。こうして両師団は4月4日までにインパール平野にたどり着いた。その間、インパールには山内正文中将の第十五師団が迫る。インパール基地を守備していた唯一の兵力、インド第50空挺旅団は前哨基地サンジャックで、コヒマへの道中にあった三十一師団の左突進隊、宮崎繁三郎少将率いる歩兵第五十八連隊と衝突し、手ひどい打撃を被った。南からは三十三師団と共に山本支隊(第72独立混成旅団)が陽動攻撃をかけていた。山本募少将率いるこの部隊は重砲多数を持った強力なもので、配下にはこの前線で唯一の戦車連隊まであった。しかしこの南からの攻撃は既に活力を失っていた。
十五、三十三の両師団がインパール包囲を始めたころ、三十一師団はインパール・ディマプール道に到達。佐藤師団長はディマプール侵攻には移らず、コヒマ周囲の丘陵地帯占領に専念した。佐藤、柳田、山内の三師団長は、あまりに補給を軽視した十五軍の作戦指導に始めから強い疑念と不安を抱いていた。獲得不可能な目標に猪突猛進する気はなかった。進軍を止めた三十一師団は4月5日集落一帯を包囲し、コヒマの戦いが始まる。丘頂上に構築された砦を巡り壮絶な争奪戦が展開された。戦闘は地区行政官のテニスコート付近で激しさを極めた。英印軍の勝利に終わるこのテニスコートの戦いは、全ビルマ戦況の転換点となる重要なものになった。4月18日、支援に駆け付けたインド第161旅団が守備隊を救出。日本軍は既に守勢に転じていたが壕を掘って粘り強く抵抗した。コヒマ戦局は長期化の兆しを見せていた。
インパールの戦いも4月に入り、戦局は日本軍にとって非常に厳しいものになっていた。インパール平野への数方向からの攻撃はいずれも英印軍防衛線に跳ね返された。インパール北に停滞した十五師団に対して、スリム中将が反攻を始めたところで雨期が訪れた。豪雨と泥濘が両軍の動きを妨げた。文字通り泥沼化した戦場で、日本兵の耐久力は尽きようとしていた。三十一、十五の両師団は 戦闘開始以来満足な補給を受けておらず、兵は飢餓に見舞われていた。佐藤師団長は牟田口軍司令官に対し、このまま無補給状態が続けば、三十一師団は5月末をもってコヒマから撤退すると一方的に通知する。師団長の無許可撤退など日本陸軍にとっては前代未聞だった。佐藤は実際撤退を命じ、宮崎少将率いる独立分遣隊を遅滞行動のためインパール・ディマプール道周辺に残すと、全軍を反転させた。後楯を失った十五師団は孤立した。兵は何とか食料を徴発しようと陣を離れさまよい歩くまでになり、もはや満足に戦える状態ではなかった。山内師団長は責任を問われ解任される。しかしこの人事刷新には何の効果もなかった。英印軍の反撃は勢いを増し、ついに6月22日、進撃する第4軍団とモンタギュー・ストップフォード中将旗下第33軍団の尖兵部隊同士がインパール・ディマプール道上109マイル地点で落ち合った。こうしてインパールの包囲は解かれた。
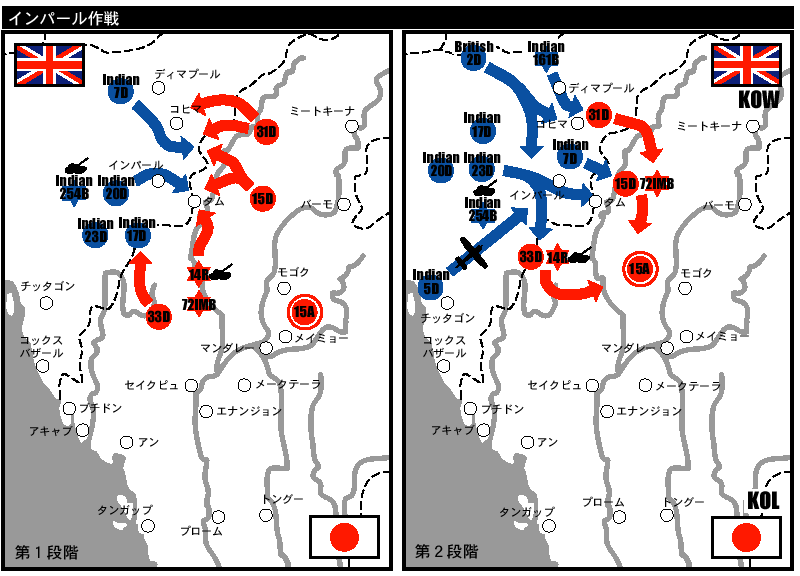
赤:日本軍 青:連合軍 二重丸:軍団以上の部隊 丸印:師団相当の部隊 星印:旅団以下の部隊
A:軍 D:師団 B:旅団 IMB:独立混成旅団 R:連隊 KOW:ノックアウト勝ち KOL:ノックアウト負け
作戦成功の望みはなくなったにも関わらず、方面軍最高指揮官河辺正三大将と牟田口は攻撃命令を出し続けた。第三十三師団正面に兵力を集中し何とかインパールに突入させようとした。三十三師団は、更迭された柳田に代わった師団長田中信男中将の厳しい指導の下、攻撃を繰り返すが、死傷者を出し過ぎ、インパールどころかその南のビシェンプールを抜くことすらできなかった。6月の終わりには、もはや何の進展も期待できなくなった。7月初旬ついに方面軍は作戦中止を決定。困憊した将兵は、チンドウィン川までの苦難に満ちた道を下がった。
インパール作戦は当時の日本陸戦史上最大の敗北となった。約一万七千五百の連合軍側死傷者数に対し、日本軍側は戦死者一万三千五百名を含む五万五千にまで及んだ。多くは退却中の飢餓、病気、疲労によるものである。失意の牟田口は方面軍から外され、不面目にシンガポールへ去った。第十五軍司令官の座は新たに、片村四八中将が占めた。佐藤中将は精神錯乱と見なされ軍法会議への起訴は見送られた。陸軍の醜聞になることを恐れた河辺大将、寺内元帥の計らいである。その河辺もまた方面軍最高指揮官の任を解かれた。後任は陸軍省次官だった木村兵太郎中将。木村は怜悧な戦略家ではあったが、闘将というよりはむしろ兵站学の専門家だった。そのため武闘派の田中新一中将が参謀長に就任した。この時期は師団長、参謀の解任、配置転換が相次いだ。
アラカン戦線1944〜45年
新指揮官木村は方面軍既存戦力の貧弱さを改めて認識した。日本軍が敵の追撃を食い止めるにはチンドウィン川沿いに防御線を引くのが常套で、それは英印軍も予測していると踏んだ木村は、敵の作戦計画を混乱させることに活路を見い出そうとした。チンドウィン川守備の代わりに当座しのぎの三作戦が作成された。第十五軍にイラワジ川左岸を守らせる「磐作戦」。第二十八軍にイラワジ川下流、アラカン防衛を命じる「完作戦」。そして第三十三軍をバーモ、ラシオ地区に下げインド中国間レド公路の開通を妨害させる「断作戦」である。
アラカンでは、雨期が終わるやクリスティソンの第15軍団がアキャブに進出。日本軍は1944年12月31日既にここを撤退しており、要衝アキャブはあっけなく奪還された。15軍団は西アフリカ第82師団に南下中の日本軍を海岸伝いに追撃させるかたわら、挟撃のため水陸両用作戦部隊を出動させた。上陸作戦はイギリス奇襲旅団が担当した。1945年1月12日、第42旅団がミエボン半島南東岸に上陸。22日には第1、第3旅団がデイボン・クリークの砂浜に上陸。海岸を固め内陸に進撃するとすぐにカンゴウで激しい戦闘になった。この海岸堡周辺の攻防戦は苛烈な白兵戦に発展し、危機を認識した日本軍は、第五十四、第五十五師団からありったけの兵力を投入した。29日になってようやく戦局を好転させた奇襲旅団はカンゴウを奪取。一方、ミエボン半島上陸部隊も、カンゴウ方面に進撃してきた西アフリカ第82師団との合流に成功していた。挟撃された日本軍は算を乱し、無数の戦死者と重火器のほとんどを残して退却した。海岸地帯を制圧した連合軍は、攻撃の手を緩めなかった。港湾設備を合せ持つ航空基地を建設するため更にチェドバ島、ラムリー島の攻略に乗り出した。日本軍が撤退していたため、チェドバ島は無血占領できたが、ラムリー島では日本兵特有の頑強さを持つ守備隊の抵抗に会い、攻略には六週間を要した。
北ビルマ1944〜45年
1944年末から蒋介石は、中国国内での日本軍の新たな反攻に対処するため、ビルマ戦線中国軍を帰国させるよう度々要求していた。そのためダニエル・サルタン中将指揮下の米中連合、「北部戦域軍」の作戦は妨げられていた。それでもサルタンは第三十三軍に対して攻勢をかけ始めた。中国軍三個師団と「マーズ旅団」として知られる米軍が、ミートキーナからバーモへ進撃。日本軍は数週間に渡って抵抗したが、12月15日バーモはついに陥落。サルタンの米中軍は1945年1月21日、国民政府雲南遠征軍との連絡に成功。戦況はいまだ不安定ではあるが、レド公路はここに開通された。続いて3月7日、ラシオを奪還すると、追撃戦による損耗を恐れた蒋介石は、これ以上中国軍を南下させないようサルタンに要求した。またその必要性も薄らいでいた。このころ既に北部戦線の日本軍への補給線は第14軍によって断ち切られようとしていた。ついに戦線を放棄した第三十三軍はイラワジ川沿いに退却を始めた。
イラワジ会戦
スリムは最初チンドウィン、イラワジの二大河川にはさまれたシュエボ平地に全軍攻撃をかけようとしていたが、日本軍が既にイラワジ対岸まで後退していると知ると、スクーンズの第4軍団をパコック付近で渡河させ、日本軍兵站中心地メークテーラ急襲に向ける戦略に出た。その一方、ストップフォードの第33軍団には予定通りシュエボ平地を進ませた。シュエボの先にはビルマ第二の都市マンダレーがある。無線通信の偽装工作で日本軍には両軍団共マンダレーを狙っていると思わせた。33軍団は、予定通り1月から2月にかけてマンダレー近くに渡河点を占領。首尾良く日本軍予備勢力を引き付けた。ビルマの制空権は既に連合軍の手中にあった。日本軍は自由に飛行機を出撃させることができず、パコックへ大兵力が進撃していることを察知できなかった。第4軍団を先導するインド第7師団は2月末、パコック近くのニャングに渡河点を確保。この時すでに機械化されていたインド第17師団は、インド第255機甲旅団と共にイラワジを越えメークテーラへ突進した。乾期の中央ビルマは砂漠のような平原に変貌する。この地では、機械化部隊の移動速度は、不意を突かれた日本軍指令部参謀たちよりはるかに優った。3月1日メークテーラに到着した部隊は四日間でここを落とした。粕谷少将率いる日本軍守備隊はにわか仕立てに過ぎなかったが、それでも決死の抵抗を見せた。戦いは壮絶さを極めた。航空爆弾を抱えたまま壕に伏せた何人もの日本兵が、真上を通過する敵戦車に対し自爆攻撃を行った。守備隊を救出しメークテーラを奪還しようと周辺から援軍が駆け付けてくると、戦いは更に激しさを増した。日本軍は八個連隊を迎撃戦に投入したが、なお数が足りなかった。また五個に及ぶ師団(二、十八、三十三、四十九、五十三)から寄せ集めたので、連携がうまく取れなかった。第三十三軍指令部にこの重大局面の指揮が委ねられたが、収拾を付けられるものではなかった。月末までに多くの死傷者を出した日本軍は、火砲のほとんどを失いピャブウェに後退した。
日本軍がメークテーラ周辺の戦闘に引き付けられている間、第33軍団はマンダレーを攻めていた。インド第19師団が市内に突入したが、日本軍守備隊は旧王宮の城塞「フォート・デュフェリン」に立てこもり激しく抵抗。凄惨な市街戦は3月19日夜、生き残った日本兵が堀の排水溝から脱出するまで一週間続いた。マンダレー奪還によってインドから中国への陸上連絡路はより安全なものになった。大損害を被った片村中将の第十五軍は小部隊に分かれ、それぞれにシャン高原へ後退した。
ペグー会戦
雨期が来ると部隊の移動は非常に困難になる。スリムは乾期の間に何とかラングーンを奪還しようと試みていた。桜井中将旗下第二十八軍の頑強な抵抗に会いながらも、ストップフォードの第33軍団はイラワジ河沿いを南下していた。その間スクーンズの第4軍団は、ピャブウェ周辺で遅滞行動に出る第三十三軍残余勢力と戦闘中だった。インド第17師団は、有力な日本軍防御陣地に動きを止められると、戦車隊と機械化歩兵部隊を迂回させ背後からこれを強襲、粉砕させた。ピャブウェの戦い以降、17師団はインド第255機甲旅団の先導でラングーンへの主要道を突き進んだ。続いてピンマナの日本軍を急襲し、街と橋を素早く確保した。この戦闘で第三十三軍は不意を突かれ、指令部までもが蹂躙された。本多軍司令官と参謀たちは命からがら脱出したが、部隊は四散してしまい、しばらく掌握不能になった。
一方、シャン高原に逃れた片村の第十五軍は、第五十六師団によって補強され態勢を立て直していた。十五軍はトングーに移動しラングーンへの主要道を封鎖することになった。しかしイギリスの息がかかったカレン族ゲリラに阻害され、行軍は度々滞った。結局、第4軍団を先導するインド第5師団が先んじてトングーを占領。続いて先鋒を引き継いだ17師団は4月25日ラングーン北64キロの街、ペグーで日本軍後衛部隊と衝突。方面軍最高指揮官木村は、ラングーンの後方勤務兵を中心に海軍陸戦隊や民間人まで投入して第百五独立混成旅団を編成し、ペグーを守らせていた。百五旅団は英印軍の進撃を少しでも遅らせようと、航空爆弾や高射砲などあらゆる武器をかき集め、最後には刺突爆雷による自爆攻撃まで繰り出して闘ったが、4月30日までにすべて排除された。このころスリムが恐れていた雨期が到来した。
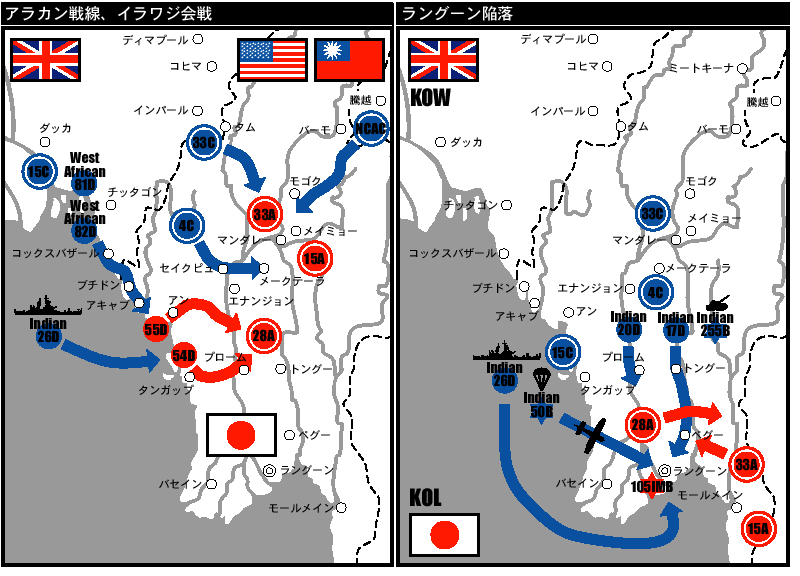
赤:日本軍 青:連合軍 二重丸:軍団以上の部隊 丸印:師団相当の部隊 星印:旅団以下の部隊
NCAC:北部戦域軍 A:軍 C:軍団 D:師団 B:旅団 IMB:独立混成旅団
KOW:ノックアウト勝ち KOL:ノックアウト負け
ラングーン陥落
英印軍は当初、第14軍のラングーン攻略に先立って、海からの補給線を確立しておくため第15軍団をベンガル湾から敵前上陸させる「オペレーション・ドラキュラ」という作戦を立てていたが、資材、輸送力の不足により、決行を見送っていた。スリムは日本軍に雨期の間首都を死守されることを恐れていた。そうなれば第14軍は補給に深刻な問題を抱えることになる。陸上連絡路は延び切っており、部隊への補給は最寄りの飛行場への航空輸送が頼りだった。来るべき豪雨は飛行場の機能を低下させ、その航空輸送さえ困難になるだろう。そこでスリムは、棚上げになっていたオペレーション・ドラキュラを至急再開できないかと上層部に打診していた。
しかし木村は既にラングーン放棄を決定していた。4月22日から多くの部隊が海路で脱出を始め、少なからず英海軍潜水艦の好餌となった。木村ほか方面軍指令部は陸路、モールメインに退いた。まだ生き残っていた第百五独立混成旅団がこの退却の殿軍を務めた。
5月1日、エレファント・ポイントに降下したグルカ落下傘大隊がラングーン河口に残った日本軍後衛を排除。翌日上陸したインド第26師団がついにラングーンを占領。5月6日、南下してきたインド第17師団と、26師団の尖兵同士がラングーン北45キロのレグで落ち合った。
シッタン突破
ペグー山系はイラワジ川とシッタン川にはさまれた丘陵地帯で、一面のジャングルにおおわれている。 アラカンから退却し、第33軍団を迎え撃っていた桜井の第二十八軍は、ここに追い詰められ立てこもっていた。二十八軍は方面軍に合流するため 敵中突破作戦を計画していた。ペグー山系を抜け、シッタン川を渡り、モールメインを目指すのである。木村はこの突破作戦援護のため、今や一個連隊程度の兵力になり下がった第三十三軍に、シッタン川を越えて牽制攻撃をかけさせた。7月3日、命令通り本多の三十三軍は、シッタン川の屈曲部に陣取ったインド第89旅団に逆襲をかけた。互いの名誉をかけたこの戦いは、雨期の真最中胸まで達するほどの濁水の中で行われた。一進一退の攻防の後の7月10日、両軍共に後退した。
だが本多の攻撃は結局時期尚早だった。二十八軍の突破作戦準備がようやく完了したのは、7月17日になってからだった。さらに悪いことに、英軍は斥候中に戦死した日本軍将校の遺体から作戦計画書を入手していた。暴露された作戦は当然悲惨な結末を迎えた。部隊は随所で伏兵の攻撃を受け、集中砲火を浴びた。その上、増水したシッタン川を間に合わせの竹製筏に頼って泳渡する際、何百もの兵が渦巻く濁流に飲み込まれて溺死した。3月にはアウン・サン将軍率いるビルマ国民軍が日本軍に反旗を翻していた。日本軍落伍兵はビルマ人ゲリラとも戦わなければならなかった。この敵中突破作戦だけで、二十八軍は全兵力のほぼ半数に及ぶ一万名近い犠牲者を出した。混迷の状況下、1945年8月15日に日本に降伏したことすら知らず、生存兵の多くはその後も彷徨を続けた。
(ウィキペディア参照)